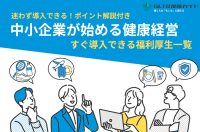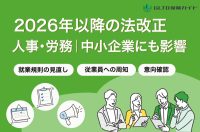GLTD(団体長期障害所得補償保険)は仕組みが少し複雑で、制度選びや設計で迷う企業も多い制度です。
本記事(後編)では、GLTDの加入方式の選び方、補償設計のポイント、導入を進める際の5つのステップを分かりやすく解説します。
自社に合ったGLTDの設計を検討したい企業の方に役立つ内容です。
▼本記事は後編です。前編の記事もあわせてチェックしてみてください▼
GLTDの基本や人気の理由、導入メリットをわかりやすく解説しています。
GLTD加入時・設計時の検討ポイント
GLTDは、会社ごとの制度・働き方・予算にあわせて、最適な形に組み立てていく保険です。ここでは、企業が導入するときに押さえておきたい主要なポイントを整理します。
① 加入方式の選択(全員加入・任意加入・ハイブリッド)
GLTDには、企業の制度設計の考え方に応じて採用される3つの加入方式があります。それぞれの特徴を理解することで、自社に合った設計方針を検討しやすくなります。
全員加入型(福利厚生型)
企業が保険料を全額負担し、従業員全員が加入する方式です。福利厚生としての公平性が高く、「会社が社員を守る」という姿勢を最も分かりやすく示せる方式です。
●メリット
・全員が同じ補償を受けられるため公平性が高い
・従業員の満足度・安心感が高い
・団体割引が効きやすく、制度として安定する
●デメリット
・企業が保険料を全額負担するため費用が大きくなりやすい
●ポイント
・健康経営や人的資本開示に力を入れている企業
・「従業員を守る」姿勢を可視化したい中堅~大企業
任意加入型
企業は団体契約だけ結び、加入するかどうかは従業員本人が選ぶ方式です。個人で加入するより割安で、必要な人が加入できるのが特徴です。
●メリット
・企業の費用負担を抑えられる
・従業員は個人加入よりも割安で加入できる
●デメリット
・加入しない層が一定数出るため公平性が弱い
・加入率が低いと制度自体の認知が広がらない
●ポイント
・コストを抑えたい企業への導入が多い
・まず「希望者向け制度」として導入したい企業におすすめ
ハイブリッド型(全員+任意加入の上乗せ方式)
全員加入と任意加入の良い部分を組み合わせた方式です。「最低限の補償は会社負担」「上乗せ部分は希望者が任意加入」という設計で、最近では最も導入が増えている方式です。
●メリット
・企業負担を抑えつつ、全員に最低限の補償を提供できる
・必要な人だけが保障を上乗せできるため、満足度が高い
・公平性と柔軟性を両立できる
●デメリット
制度設計がやや複雑で、説明や運用の準備が必要
●こういった企業におすすめ
・全員をカバーしたいが、費用は抑えたい
・社員の価値観やライフステージが多様化している企業
・福利厚生を柔軟かつ公平に運用したい
📌 税法上のメリット
全員加入型:企業が負担した保険料は福利厚生費として全額損金処理が可能です。
任意加入型:個人が負担した保険料は、年末調整時に保険料控除の対象となります。
②補償額(保険金額)の設定:定額型か定率型か
GLTDの補償額は「定額型」と「定率型」のどちらを採用するかによって、制度の分かりやすさやコストに差が出ます。 それぞれにメリット・デメリットがあるため、企業の目的や従業員の給与水準に合わせて検討することが大切です。定額型
月5万、10万、15万円といった、一定額を補償する方式です。制度がシンプルで理解しやすく、任意加入方式や労働組合・共済会などの見舞金制度にも適しています。- メリット:補償内容が分かりやすく、説明・運用が容易。従業員が「何口加入するか」を選べるため、任意加入方式と相性が良い。
- デメリット:給与水準に関わらず同一額のため、年収差が大きい企業では十分な補償にならないケースがある。
定率型
給与の○%を補償する方式で、生活水準に応じた実質的な補償が可能です。GLTDの標準的な設計であり、全員加入方式との相性が良いのが特徴です。- メリット:生活レベルに合わせて補償額が変動し、実態に沿った補償が可能。高年収層にも十分な補償を確保できる。
- デメリット:給与(標準報酬月額)を基準とするため、制度理解に一定の説明が必要。
📌 公的給付控除の有無(定率型のみ)
定率型では「公的給付控除あり/なし」の2つの設計から選択ができます。
- 公的給付控除あり:傷病手当金や障害年金などの公的給付を差し引いた不足分に対して一定割合を補償。
→企業負担の保険料を抑えやすい。 - 公的給付控除なし:公的給付を控除せずに、所得そのものに対して一定割合を補償。
→補償は手厚いが、その分保険料は高くなりやすい。
③免責期間・補償期間・補償範囲の設計
GLTDでは、「いつから・いつまで・どこまで補償するか」を柔軟に設計できます。制度の使いやすさやコストに大きく影響するため、導入時に特に注意すべきポイントです。
免責期間(支払い開始までの待ち期間)
免責期間とは、働けなくなってすぐに保険金が支払われるのではなく、一定日数は対象外とする「待ち期間」のことです。 一般的には30日・60日・90日で設定します。- メリット:免責期間を長くするほど保険料を抑えやすい。
- デメリット:その期間の収入を別制度で確保する必要があり、休職制度との整合性が重要。
企業の休職制度(有給、欠勤控除、傷病手当金の開始時期など)に合わせて免責期間を調整すると、負担と安心のバランスが取りやすくなります。
例:有給+欠勤調整で「最初の60日は収入が確保できる」場合、GLTDは60日免責にするなど。
補償期間(いつまで支給されるか)
補償期間には、以下の2つの方式があります。● 歳満了型(60歳・65歳・70歳など)
- メリット:長期にわたり安定的に従業員を支援でき、制度としての安心感が高い。
- デメリット:補償が長期化する分、保険料は上がりやすい。
- メリット:費用を抑えつつ、一定期間の休職リスクに備えられる。
- デメリット:設定期間を過ぎると補償が終了するため、長期化した場合の安心感は弱い。
補償範囲(どこまでを対象にするか)
GLTDでは、補償する範囲を企業の方針にあわせて設定できます。● 24時間補償(業務内・業務外すべて対象)
- メリット:従業員に最も安心を提供でき、GLTD本来の意義を最大化できる。
- デメリット:補償範囲が広いため、保険料は高めになる。
- メリット:費用を抑えやすく、最低限の備えとして導入しやすい。
- デメリット:業務中の事故・病気は対象外となり、制度としての安心感は低くなる。
④特約の範囲と社内制度との整合性
GLTDの価値を左右するポイントとして、「どこまで補償範囲を広げるか」「社内制度とどう整合させるか」が非常に重要です。特約の設計は保険会社により異なりますが、ここでは代表的な特約を説明します。
代表的なオプション・特約の例
・天災危険補償特約:地震や噴火などにによる所得喪失をカバー・リハビリ勤務を支援:短時間勤務でも補償が継続可能
・メンタル疾患特約:うつ病など精神疾患による所得喪失をカバー
・妊娠出産特約:妊娠悪阻・妊娠高血圧症候群などを補償対象に含む
・介護支援特約:介護休業周りの所得減の補償(※各保険会社により内容が異なる)
ポイント:
女性従業員が多い企業では、これらの特約の有無が制度満足度に大きく影響します。意外と見落とされがちなポイントですが、検討価値の高い項目です。
社内制度との整合性
GLTDの設計で最も重要なのが、「既存の社内制度との整合性」です。どの制度を補完し、どこからGLTDがカバーするのかを明確にしておかないと、運用時に混乱が生じます。
● 整合性を確認すべき社内制度の例
- 休職制度(期間・給与の有無)
- 復職判定のルール
- 傷病手当金などの公的給付の取り扱い
- 就業規則・休業規程・人事制度
GLTDは「どこからが保険の役割なのか」を明確にしておく必要があります。 制度が曖昧だと以下のような誤解が生まれやすくなります。
- 「GLTDがあるなら有給を使わなくても良いの?」
- 「復職判定が通らなかった場合、保険金はどうなるの?」

GLTD導入の進め方:5つのステップ
GLTDは福利厚生としての役割に加え、従業員の生活と企業の持続性を守る経営施策でもあります。 「どう導入すれば良いか分からない」という企業のために、実際の導入プロセスを5つのステップで整理しました。ステップ1:自社の現状整理
GLTDは「福利厚生の充実」だけでなく、従業員の生活と企業のレジリエンスを支える仕組みでもあります。 導入にあたっては、以下の視点を意識すると、効果的な制度設計ができます。- 長期休職者の発生状況(メンタル・病気・家庭事情など)
- 従業員からの福利厚生ニーズ
- 健康経営・人的資本開示など、経営方針との整合性
- 従業員の年齢構成・勤続年数・将来リスク
GLTD導入を検討する際に押さえておきたいポイント
GLTDは「福利厚生の充実」だけでなく、従業員の生活と企業のレジリエンスを支える仕組みでもあります。 導入にあたっては、以下の視点を意識すると、効果的な制度設計ができます。- 自社の人材戦略と補償内容が整合しているか
- 長期休職リスクにどれだけ備えたいか(経営判断)
- 採用・定着といった企業ブランディングへの影響
- 競合他社との差別化ポイントとしての活用
ステップ2:複数社からの見積もり取得
GLTD導入の際は、まず複数の保険会社の見積もりを取得し、補償内容と保険料の目安を把握することが重要です。 GLTDは一般的な保険とは異なり、企業ごとに制度設計が必要な“オーダーメイド型の福利厚生制度”のため、比較検討が欠かせません。■ なぜ複数社の比較が必要なのか
- 補償範囲・免責期間・てん補期間など、設計条件が大きく異なる
- メンタル疾患や妊娠・出産に関する特約の扱いが保険会社ごとに違う
- 付帯サービス(復職支援、健康相談、メンタルサポートなど)の充実度に差がある
■ 見積依頼時に確認したいポイント
- 免責期間・補償期間・補償範囲の違い
- メンタル疾患・妊娠出産に関する特約の有無
- 付帯サービス(健康相談、復職支援プログラムなど)の内容
- 企業規模・年齢構成に応じた保険料の差
ステップ3:補償プランの設計を固める
複数社の見積もりと自社の状況整理を踏まえ、GLTDの補償設計を具体化していきます。 GLTDは企業ごとに制度をつくる“オーダーメイド型”のため、設計次第で制度価値も保険料も大きく変わります。■ 設計時に決める主な項目
- 加入方式(全員加入型か、任意加入型か)
- 補償額(定額型/定率型、公的給付控除あり/なし)
- 免責期間(30日・60日・90日)
- 補償期間(歳満了型/期間満了型)
- 補償範囲(24時間補償/業務外のみ)
- メンタル疾患・妊娠出産などの特約
■ 専門担当者に相談したほうが良い理由
GLTDは制度設計の自由度が高く、各社の設計条件にも大きな違いがあります。 そのため、一般の保険代理店では制度全体を設計できないことも多く、次のような落とし穴が起こりがちです。
- 免責期間と休職制度が噛み合わず、収入の空白期間が発生する
- 補償割合が実生活に合っておらず、いざという時に不足が出る
- 任意加入型を選んだが加入率が低く制度が機能しない
- グループ会社や出向者の扱いが曖昧でトラブルになる
📌 補償設計の見落としでトラブルになったケース
- 待機期間を180日に設定したが、傷病手当金の終了後に“無収入の空白期間”が発生。
→ 免責期間と休職制度の整合性を見直していれば防げた。 - 補償割合を50%にしたところ、住宅ローンや教育費を考えると生活が維持できなかった。
→ 「生活コスト」を試算して補償額を決めるべきだった。 - 任意加入型にしたが、制度理解不足で加入率が低く、制度として機能しなかった。
→ 全員加入型(福利厚生型)なら全従業員をカバーできた。 - 子会社・グループ会社の社員が対象外だったため、出向時に補償の有無でトラブルに。
→ 保険料負担や就業規則の整備まで含めて設計すべきだった。
ステップ4:社内説明・同意を得る
GLTDは「任意加入型」と「全員加入型(自動加入型)」のどちらを採用するかによって、社内での説明方法や合意形成のプロセスが変わります。 福利厚生制度として導入する場合は、会社負担または折半型が一般的で、人事・総務・経営層で方向性を統一しておくことが重要です。制度を正しく理解してもらい、従業員が納得して加入判断できるよう、社内説明のプロセスを丁寧に行う必要があります。
💡GLTD導入時の社内説明で押さえておきたいポイント
■ 社内への説明で重要なこと
- 説明資料の作成:GLTDの仕組み、補償内容、会社負担の範囲、保険金請求の流れなどを分かりやすくまとめて配布。
- 説明会・質疑応答:制度の目的や加入方法を説明し、従業員の不安・疑問に丁寧に回答する時間を設ける。
- 対象範囲の明確化:正社員・契約社員・パートなど雇用形態によって補償範囲が異なる場合は、その違いを明示する。
- 個別相談の実施:希望者には家計やライフプランに応じた個別相談を提供し、加入判断をサポート。
■ 従業員に特に伝えたいポイント
- GLTDは団体制度で加入できる:個人加入より保険料が割安で、補償期間が長く設定できるケースが多い。
- 個人保険との重複に注意:GLTDの内容を理解せずに個人で保険に入ると補償が重複する可能性がある。
- 制度の理解が“安心”につながる:「もし働けなくなったら?」という不安軽減に役立ち、従業員満足度にもつながる。
当社では、ご希望に応じて社員説明会・質疑応答・個別相談までサポートすることも可能です。
ステップ5:保険会社との契約・運用開始
補償プランが決まり、社内合意が得られたら、いよいよ契約手続きに進みます。 契約後は、制度内容を社内イントラネットや説明会で共有し、運用ルールを明確にすることが重要です。 GLTDは導入して終わりではなく、毎年の従業員数や構成の変化に合わせて見直しが必要な“運用型の福利厚生制度”です。■ 主な管理ポイント
1. 保険料の増減管理
- 全員加入型(会社負担): 従業員数の増減に伴い、会社負担総額も変動します。
- 任意加入型(従業員負担あり): 加入人数により会社・従業員双方の保険料が変わります。
- 固定費用の調整: 社員の増減により、GLTD制度にかかる固定費(付帯サービス費用など)が上下することがあります。
2. 給付金・給与水準との連動
- 給付対象者の変動: 支給対象となる従業員数によって、保険会社側の支払い総額が変わり、更新時の料率に影響する場合があります。
- 給与水準の変化: 定率型の場合、給与ベースの増減により補償額が調整されることがあります。
3. 事務手続き・日常運用
- 入退社の対応: 新入社員への制度説明や加入案内、退職者への脱退案内など、基本的な人事フローとリンクさせることが必要です。
- 名簿管理と更新: 毎年の従業員名簿をもとに保険料を再計算し、代理店を通じて保険会社へ報告します。
- 誤解防止: 退職後は補償が終了する点を明確に伝えることでトラブルを防げます。
■ 運用時に特に注意したいポイント
- 契約内容の明確化: 全員加入型か任意加入型かによって、税務処理や保険料計算が異なるため、導入時に条件を整理しておくことが重要です。
- 年次更新と見直し: 年1回の更新タイミングで、補償内容や対象人数を見直し、会社の状況と合っているか確認します。
- 代理店との連携: 専門代理店が伴走し、更新・請求・設計変更のサポートを行うことで、制度の安定運用につながります。
- 制度説明の継続: 新入社員・異動者へ制度説明を継続することで、制度の定着と従業員の安心感を維持できます。
まとめ:GLTDで「働けないリスク」に備える仕組みを整える
GLTD(団体長期障害所得補償保険)は、病気やケガで長期間働けなくなった場合に、 従業員の生活を継続的に支えることができる数少ない福利厚生制度です。 医療保険や生命保険が「治療」や「万一の備え」にフォーカスしているのに対し、 GLTDは“働けない期間そのものの生活費”をカバーできる点が大きな特徴です。近年では、
- 健康経営
- 人的資本経営
- ウェルビーイングの向上
- 離職防止・エンゲージメント向上