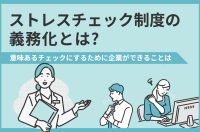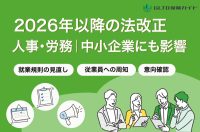企業のホームページや名刺で「●●認定企業」などのロゴマークを見かけたことがありませんか?
このロゴマークは、官公庁や公的機関などで実施されている認定制度の証です。
各制度の基準を満たせば申請・認定を受けてロゴマークを活用できるため、企業は対外的なイメージアップをはかることができます。
今回は、中小企業こそ活用メリットが大きい企業認定制度についてご紹介します。採用活動に力を入れたい企業は、導入を考えてみましょう。
企業認定制度を使うメリット
企業認定制度の取得によって得られる主なメリットは以下の3つです。1.企業ブランディングになる
企業認定制度では「女性活躍推進企業」「子育て支援が手厚い企業」など、特定のテーマに沿ったイメージアップ戦略が可能です。求人サイトなどの広報物にロゴマークを使用すれば企業ブランディングにもなり、市場での認知度向上や人材の定着にもつながるでしょう。
2.助成金・補助金申請が有利になる
企業認定制度の中には、認定によって助成金や補助金などの資金調達が有利になる場合があります。たとえば、厚生労働省の認定企業制度では、認定企業の公共調達において加点評価をすることが国の指針で定められています。
3.公的融資で優遇措置がある
金利割引など、公的融資の優遇措置を受けられる制度もあります。特に多いのは日本政策金融公庫の低利融資で、特定の融資を利用する際、基準利率よりも低い金利での融資を受けることが可能です。資金調達の選択肢が増えるのは企業にとってありがたいメリットです。
【一覧】官公庁・公的機関の企業認定制度10選
ここでは、中小企業が活用しやすい企業認定制度をご紹介します。1.各種くるみん|厚生労働省
厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定する制度です。次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の基準を満たした企業が対象です。「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」に加えて、2022年4月からは「トライくるみん認定」「プラス認定」がスタートしています。
【メリット】
認定を受けた企業は、各種くるみんのロゴマークを広報物に表示でき、「子育てサポートに手厚い企業としてアピールできます。また、中小企業は関連する助成金の申請が可能になります。
参考:厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」
認定を受けた中小企業は「くるみん助成金」を申請できる
各種くるみん認定を取得した中小企業は、「くるみん助成金」を申請できるようになります。助成金の対象になるのは、労働者の仕事と家庭生活との両立のために必要な雇用環境の整備を行う事業の経費です。育児休業等の取得や子育て支援の取り組みなどを行う場合、50万円を上限に経費の助成金を申請できます。助成金の概要は毎年変わるため、詳細は「くるみん助成金ポータルサイト」にてご確認ください。
2.健康経営優良法人認定制度|経済産業省
特に優良な健康経営を実践している企業を対象に、日本健康会議が認定する制度です。制度設計は経済産業省で、認定は日本健康会議(実行委員は経団連や日本商工会議所など)が行います。大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2部門があります。【メリット】
認定企業は「健康経営優良法人」ロゴマークの使用が可能となるほか、自治体や金融機関においてさまざまなインセンティブが受けられます。
参考:経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
3.えるぼし認定・プラチナえるぼし認定|厚生労働省
女性の活躍を推進する企業に対して、厚生労働大臣が与える認定制度です。2016年に全面施行された女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍状況を把握・分析し、所定の計画を立てて取り組みを行った企業が対象です。常時雇用する労働者が101人以上いる企業の場合、自社の女性の活躍に関する状況を自社のホームページ等で公表する義務があります。【メリット】
認定マークを各種広報物・商品に使用できます。また、認定を受けた企業は補助金等の公共調達において加点評価を受けられます。
参考:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
4.ユースエール認定制度|厚生労働省
若者の採用・育成に積極的で、かつ若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。若年層の採用に力を入れたい企業に適しています。【メリット】
認定マークを各種広報物・商品に使用できます。また、ハローワークや厚生労働省の運営サイト等を通じて若者にPRできます。日本政策金融公庫による融資制度の優遇など、多数のメリットがあります。
参考:厚生労働省「ユースエール認定制度」
5.安全衛生優良企業認定|厚生労働省
労働者の安全や健康確保に積極的に取り組み、高い水準で安全衛生水準を維持・改善している企業を厚生労働省が認定する制度です。【メリット】
認定マークを活用し、安心して健康的な働き方ができる企業であることをアピールできます。求職者にPRできる。また、厚生労働省のホームページでも認定を受けた企業名が公表されます。
参考:厚生労働省「安全衛生優良企業 参考資料」
6.もにす認定制度|厚生労働省
障害者の雇用と雇用の安定を積極的に行う中小企業を対象に、厚生労働大臣が認定する制度です。【メリット】
認定マークを各種広報物や商品に使用できます。日本政策金融公庫の低利融資対象になるほか、認定企業は厚生労働省および都道府県労働局のホームページに掲載されます。
参考:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」
7.エコ・ファースト制度|環境省
環境分野において先進的、独自的でかつ波及効果のある事業活動を行っている企業を対象に、環境大臣が「業界における環境先進企業」と認定する制度です。企業は環境大臣に対し、地球温暖化対策や廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取り組みを約束する必要があります。【メリット】
認定を受けた企業は、各種広報物や商品にエコ・ファーストマークを使用できます。また、環境政策の最新情報を入手したり、環境庁の調達案件で加点対象となったりします。
参考:環境省「エコ・ファースト制度」
8.DX認定制度|経済産業省
「情報処理の促進に関する法律」に基づき、積極的にDX経営に取り組む企業を国が認定する制度です。DX認定企業は全国的に増えており、特に中小企業等では直近1年間(2024年10月時点)で約2.0倍の伸びを見せています。【メリット】
認定企業は、DX認定制度ロゴマークをホームページや名刺等で使用できます。また、中小企業を対象とした日本政策金融公庫による金利優遇、信用保証協会による別枠での追加保証や保証枠の拡大措置などの金融支援措置のほか、税制による支援措置や人材支援措置などがあります。
参考:経済産業省「DX認定制度」
9.「事業継続力強化計画」認定制度|経済産業省
中小企業が防災・減災の事前対策をまとめた計画について、経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。中小企業向けの簡易なBCPとして位置づけられています。【メリット】
認定企業は、国の各補助金事業において、加点措置を受けることができるほか、税制措置や金融支援などの支援策が受けられます。また、損害保険料の割引を受けられることもあります。
参考:中小企業庁「事業継続力強化計画」
10.東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度|東京都
こちらは東京都内に本社や主たる事業所を置く中小企業や財団法人等(従業員300人以下)限定の認定企業制度です。ワークライフバランスの実現に向けて、優れた取り組みを行う企業を東京都が認定します。【メリット】
自社サイトやパンフレットなどの広報物に認定マークを使用できます。また、東京都の公式サイト等で企業名が掲載・周知されるほか、東京都が行う入札において、加点になる場合があります。毎年、認定企業の中から大賞と優秀賞がさらに選定され、認定状授与式で発表・表彰されています。
参考:東京都「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度」
東京都以外でも、各自治体でこうした認定企業制度を実施していることがあります。所在地の自治体で探してみてください。

そのほか:民間の認証制度など
官公庁や公的機関以外でも、さまざまな民間団体が認証制度やシンボルマークを提供しています。対外的にアピールしたいテーマがあれば、あわせて活用を検討してみましょう。ハタラクエール|民間の認証制度
福利厚生の充実・活用に力を入れる企業を表彰・認証する、民間の福利厚生表彰認証制度です。民間の認証制度ですが、実行委員には日本生命や野村證券、三井住友信託銀行など著名な企業が名を連ねています。【メリット】
エントリー料は不要で、応募・審査・表彰等に一切費用はかかりません。認証されれば、福利厚生に力を入れる企業として対外的なアピールが可能です。
参考:ハタラクエール 福利厚生表彰・認証制度
トモニン|シンボルマーク
「仕事と介護を両立できる職場」の整備促進のためのシンボルマークです。こちらは認定制度ではないため、職場環境の整備促進に関する取り組み内容を登録することですぐシンボルマークを活用できます。
【メリット】
応募や審査がなく、使用規定に了承した対象企業はすぐにシンボルマークを使用できます。
参考:厚生労働省「「トモニン」を活用して、仕事と介護の両立支援の取組をアピールしましょう! 」
まとめ
企業認定制度を活用すれば、特定のテーマに沿った企業ブランディングが可能です。対外的なイメージアップだけではなく、企業イメージの定着にもつながるでしょう。また、各種補助金・助成金の申請や公的融資の優遇措置など、資金調達の面でも種々のメリットがあるため、上手に活用することをおすすめします。
「従業員を大切にする企業」「福利厚生が充実した企業」というアピールをする場合は、GLTD(団体長期障害所得補償保険)の導入という方法もあります。中小企業でできる対策を考えている人は、あわせて検討してみてください。