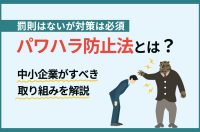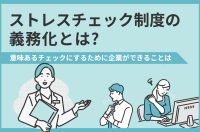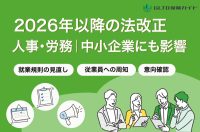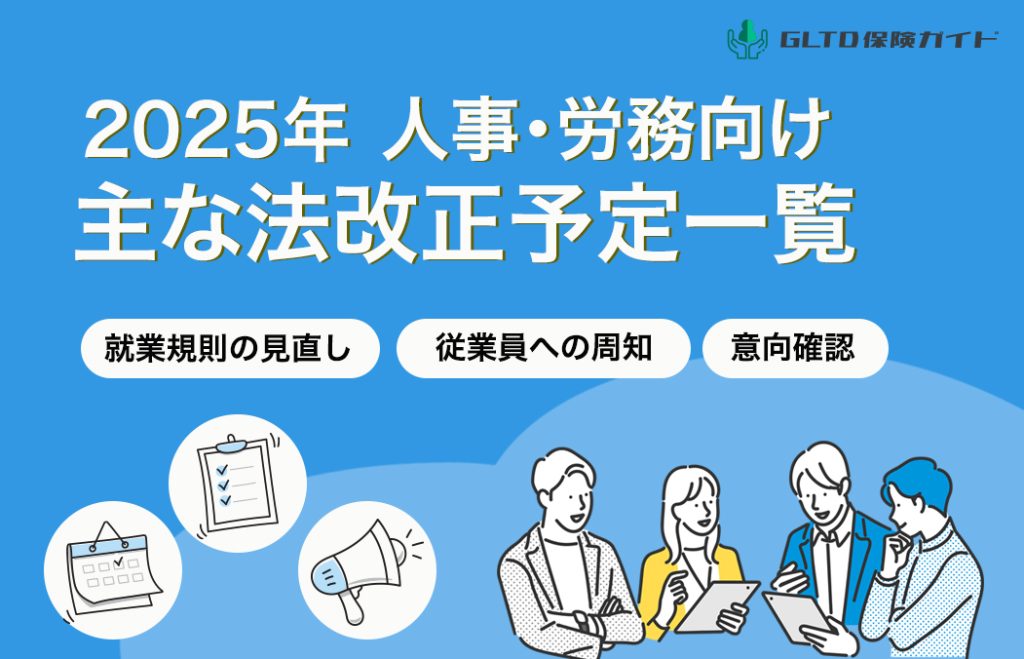
2025年は、人事・労務の実務に大きな変化が訪れる年です。
育児・介護休業制度の見直しや雇用保険制度の改正など、働き方や福利厚生に直結する重要な法改正が次々と施行されます。これらの改正は、企業にとって単なる制度変更にとどまらず、従業員の雇用環境や社内手続きに対する新たな対応を迫るものです。
本記事では、2025年に予定されている主な法改正を時系列で整理し、それぞれの改正ポイントや企業として押さえておくべき実務対応についてわかりやすく解説します。
▼あわせて読みたい|今後の法改正を整理した記事▼
人事・労務分野の法改正は、2025年以降も段階的に続く見通しです。 2026年以降の主な改正内容と、人事担当者が押さえておきたい実務ポイントを 別記事で整理しています。
人事・労務関連の主な法改正予定一覧【2026年以降】 人事担当者が押さえておきたい実務ポイント 今後数年の法改正スケジュールを把握したい方はこちら2025年 法改正予定一覧
| 施行時期 | 関連法 | 主な変更内容 |
|---|---|---|
| 2025年4月 | 育児介護休業法 |
|
| 2025年4月 | 雇用保険法(育児関係) |
|
| 2025年4月 | 雇用保険法 |
|
| 2025年4月 | 健康保険法 | 協会けんぽの任意継続被保険者について標準報酬月額上限を30万→32万円に引き上げ |
| 2025年10月 | 育児介護休業法 |
|
| 2025年10月 | 雇用保険法 | 教育訓練休暇給付金の新設 |
| 2026年4月 | 子ども子育て支援法 | 子ども子育て支援金を健康保険に上乗せして徴収 |
| 2026年7月 | 障害者雇用促進法 | 障害者雇用率を2.5%→2.7%に |
| 2027年(未定) | 出入国管理法など | 技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設 |
| 2028年10月 | 雇用保険法 | 雇用保険の適用拡大(週10時間以上のパートなど) |
▼今後の法改正も確認したい方へ
人事・労務関連の主な法改正予定一覧【2026年以降】人事担当者が押さえておきたいポイント

2025年の法改正のポイント
2025年は、4月と10月に「育児・介護休業法」の改正が予定されており、育児だけでなく介護に関する制度も大きく拡充されます。就業規則の見直しや、従業員への個別周知・意向確認など、実務面での対応が求められるため、早めの準備が必要です。
また、同じく4月からは、育児に関する新たな給付制度「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付の創設」が2つ創設されます。
特に、時短勤務社員への給付が行われる点は大きなポイントです。対象となる従業員への案内をし、申請漏れが起きないよう注意しましょう。
2026年以降の法改正は?
来年以降の変更予定も、人事・労務に関連のある法改正が続いています。特に1月に厚生労働省より労働基準法などの見直しに向けて議論をしてきた「労働基準関係法制研究会」の報告書が公表されました。
テレワークやIT技術の発展、副業の増加など働き方の多様化が進む中で、現行の労働基準法では対応できない課題が増えているため、たくさんの論点について見直しの方向性が示されております。
以下は今後変更になる可能性が高いポイントです。
▼今後の法改正も確認したい方へ
人事・労務関連の主な法改正予定一覧【2026年以降】人事担当者が押さえておきたいポイント
「労働基準関係法制研究会」の報告書のポイント抜粋
■労働時間規制の改革・勤務間インターバル制度の義務化
・在宅勤務自に適用できるフレックスタイム
■休日・休暇制度の見直し(13日を超える連続勤務の禁止)
■副業時の割増賃金の通算の廃止
■新しい働き方を見据えた労働者の定義の見直し
■労使コミュニケーションの改善
参考サイト:厚生労働省「労働基準関係法制研究会 報告書」
まとめ
法改正への備えは、企業のコンプライアンス対応はもちろん、従業員満足度やエンゲージメントの向上にも直結します。ぜひ、貴社の人事・労務管理の参考にしていただければ幸いです。もし貴社が「従業員を大切にする企業」「福利厚生が充実した企業」というアピールをする場合は、GLTD(団体長期障害所得補償保険)の導入という方法もあります。中小企業でできる対策を考えている人は、あわせて検討してみてください。
よくある質問
Q.2025年の法改正はいつから施行されますか?A.2025年は4月と10月に「育児・介護休業法」の改正が予定されています。さらに4月からは「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」など新しい給付制度も創設されるため、早めの就業規則見直しと従業員への周知が必要です。
Q.中小企業に特に影響が大きい改正は何ですか?
A.中小企業では、育児・介護休業に関する制度変更が最も影響します。特に介護に関する制度拡充は対応が遅れがちな分野のため、従業員への意向確認や制度導入の準備を早めに進めることが重要です。
Q.就業規則の改定は必須ですか?
A.法改正により新制度が導入される場合は、就業規則の改定や従業員への周知義務が生じるケースがあります。形式的な修正だけでなく、実際に運用できる体制を整えることがポイントです。
Q.法改正対応で最初に着手すべきことは?
A.まずは自社の現行制度と改正内容を照合し、影響範囲を整理することです。その上で、従業員に対する説明・意向確認、就業規則改定、申請実務の準備を進めることが求められます。
Q.法改正とあわせて福利厚生も見直すべき?
A.はい。法改正はコンプライアンス対応にとどまらず、従業員のエンゲージメント向上につなげる好機です。近年はGLTD(団体長期障害所得補償保険)のように、法改正対応と親和性の高い福利厚生施策を導入する企業も増えています。