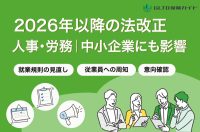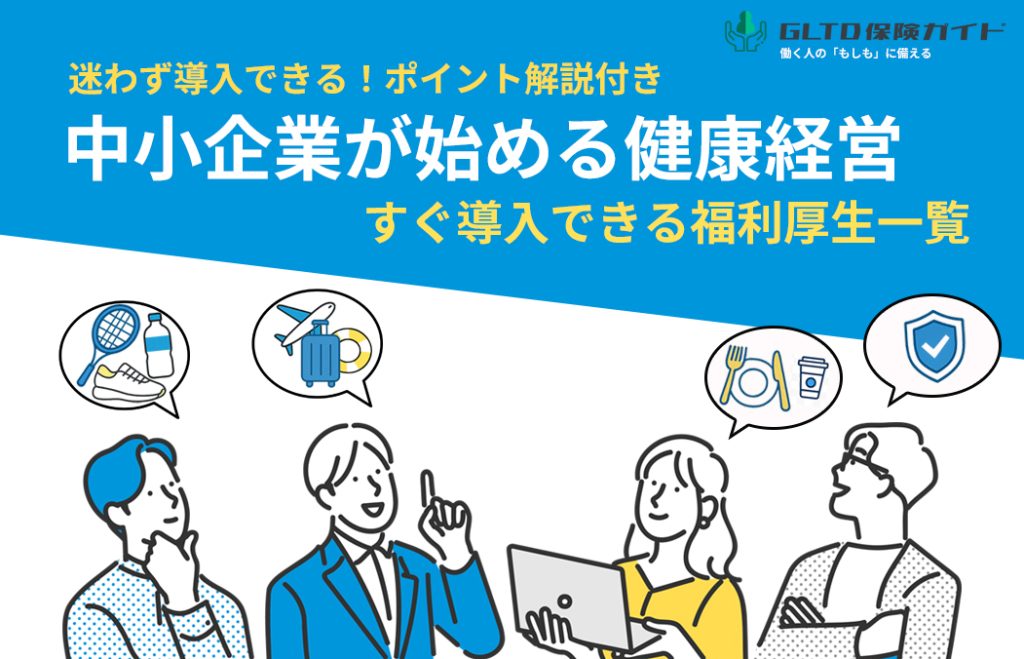
企業の競争力強化や人材確保の観点から、健康経営の考え方が広まっています。
一方で「重要性は理解しているものの、何から始めるべきかわからない」という企業もあるでしょう。特に、人員や予算に限りのある中小企業では、新しい取り組みを行うハードルが高いのが実情です。
そこで本記事では、中小企業でも取り入れやすい健康経営につながる福利厚生サービスをカテゴリ別に紹介します。
導入のポイントや効果もあわせて解説するため、自社に合った施策を探すときの参考にしてください。
【一覧表】健康経営に役立つ中小企業向け福利厚生サービス
健康経営に役立つ、中小企業向けの福利厚生サービスを紹介します。1.健康管理サービスの導入
●健康診断・人間ドック補助
法定の健康診断に加えて、オプション検診や人間ドック、がん・婦人科検診などの費用を企業が一部または全額補助します。定期的な健康チェックにより、病気の早期発見・早期治療につなげられます。●健康促進アプリ・サービスの提供
健康管理アプリ、活動量計などのデバイスを法人契約し、従業員に提供します。これらのアプリやデバイスでは、日々の歩数や睡眠時間、食事・運動内容などを記録して分析できるため、健康意識を高めて生活習慣の改善を促進できます。2.食事・栄養サポート
●健康的なお弁当の補助
栄養バランスに配慮した弁当を社内で購入できるサービスを導入し、その費用を企業が補助します。業務が忙しい中でも、従業員が健康的な食事を取りやすくなります。また、昼食を買いに行く手間を省けるため、従業員にとっては休憩時間を有効活用できるメリットもあります。●サプリメント・健康食品の購入補助
職場の休憩室にサプリメントや健康食品を設置しておき、従業員が安価に購入できるように費用を補助します。職場で手軽に栄養補給できる環境を作ることで、従業員の健康維持をサポートできます。3.メンタルヘルス支援
●外部の従業員支援プログラム(EAP)の提供
外部の専門機関にメンタルヘルスの相談業務を委託する、外部の従業員支援プログラム(通称「外部EAP」)を導入します。外部の相談窓口は従業員にとっても使いやすく、プライバシーを守りながら心のケアに努めることができます。●(従業員数49人以下の場合)ストレスチェックサービスの実施
従業員50人以上の事業所では、従業員のストレスチェックが義務化されています。現段階では対象外の企業でも自主的に実施することで、適切なケアにつなげやすくなります。メンタルヘルスの不調は当事者自身も無自覚なケースが多くあります。従業員本人が心の不調を自覚するためにも、定期的なストレスチェックを行いましょう。
▼ストレスチェックについては、下記の記事をお読みください。
ストレスチェック制度の義務化とは?意味あるチェックにするため企業ができることは
4.フィットネス・運動促進
●フィットネスジムの法人契約
近隣のフィットネスジムと法人契約を結び、従業員の利用料を一部補助します。定期的な運動機会を提供することで従業員の健康増進に貢献できます。●フィットネスエリアを作る
オフィスに簡易的なフィットネスエリアを設け、休憩時間に体を動かせる環境を作ります。空いているスペースにバランスボールやストレッチポールなどを置けば、比較的コストをかけずにフィットネスエリアを設置できます。昼食後に少し体を動かすと眠気対策にもなり、健康維持のほか、業務効率の向上にも役立ちます。5.法定外休暇の支援
法定の休暇制度に加えて、企業独自の法定外休暇制度を設けて、従業員のワークライフバランスを支援します。●法定外休暇の例
・慶弔休暇:結婚や親族の葬式・法事など慶事・弔事の際に取得できる休暇・誕生日休暇:自身や家族の誕生日に取得できる休暇
・不妊治療休暇:不妊治療のために通院する際に取得できる休暇
・看護休暇:法定を超える日数の看護休暇を付与する
・子どもの学校行事休暇:参観日や運動会などの学校行事に参加するための休暇
法定外休暇は比較的取り入れやすく、採用時にもアピールしやすい福利厚生サービスです。あらかじめ取得しやすい休暇制度を整備しておけば、急な欠勤による業務への影響も軽減できるでしょう。
6.健康増進セミナー・イベントの実施
●業務時間内の健康イベント開催
朝礼時や昼休憩後にラジオ体操やストレッチを行う時間を導入し、業務時間内に短時間の健康活動を取り入れます。全社で取り組むことで健康活動に参加するハードルを引き下げ、従業員の健康増進を期待できます。●健康セミナー・健康教室の受講支援
健康に関するセミナーや健康教室の受講費用を企業が支援する方法です。業務時間内に参加できるように調整すれば従業員の負担も少なく、気兼ねなく参加できます。正しい健康知識を得る機会や運動機会を無理なく提供し、従業員の健康意識を高められます。7.団体保険の導入
企業・団体向け保険を導入し、健康に関する不安を解消できる保障を従業員に提供する方法です。●団体長期障害所得補償保険(GLTD)
GLTDは、病気やケガで長期休業した際の収入減少をカバーする団体保険です。団体保険の中でも比較的低コストで導入できるため、中小企業でも備えやすい福利厚生の一つです。GLTDの特徴は、標準報酬月額の一定割合を最長60歳まで補償できるため、公的保障だけではカバーしきれない休業時の収入不足をしっかりとサポートできる点にあります。また、無料付帯サービスが充実しているため、補償+αの福利厚生サービスを用意できます。
【GLTDの主な無料付帯サービス】
・ストレスチェックサービス
・メンタルヘルスに関する電話相談サービス
・メンタルヘルスによる休職時・復職時のサポート
・健康・医療・介護に関する電話相談サービス
・セカンドオピニオンの提供
など
団体保険の導入方法は主に「従業員が全員加入して企業が保険料を全額負担」と「従業員が任意で加入し保険料も従業員負担」とする方法があります。
「福利厚生を見直したい」「制度設計のヒントが欲しい」そんな企業様へ。
福利厚生の最新動向やGLTD導入のメリットをまとめたホワイトペーパーをダウンロードいただけます。
資料を入手する
福利厚生サービスの導入ポイント
福利厚生サービスを導入する際は、以下のポイントを押さえておくことが重要です。従業員のニーズを把握する
どれほど評判の良いサービスでも、自社の従業員にフィットしなければ効果は限定的です。従業員の性別・年齢・家族構成によって適したサービスは異なるため、事前にアンケートを実施したり、現場の声を聞いたりして、ニーズを的確に把握しておきましょう。たとえば、子育て世代が多い職場であれば、看護休暇の拡充や子どもの学校行事休暇の導入が効果的です。一方で若手社員が多い職場では、フィットネスジムの法人契約や健康的な食事サポートが喜ばれる可能性があります。
通常業務に支障の無い範囲で始められる
福利厚生は従業員全員にとってのサービスです。サービスの導入により、一部の従業員の業務負担が増えてしまうことがないように気を付けましょう。たとえば、導入サービスの仕組みが複雑な場合、各従業員から人事・総務窓口に質問や問合せが集中する可能性があります。既存の商品やサービス、仕組みを活用し、導入と運用の手間が少ないものから検討することをおすすめします。
効果測定をどうするか決めておく
福利厚生は導入がゴールではありません。導入後には利用率や従業員の満足度、欠勤率・離職率の変化、費用対効果の分析などを行い、あらゆる角度でサービスの効果測定を行いましょう。万が一効果が見られなかった場合にはどうするのか、サービスの継続・中止を判断する際の指標も事前に決めておくとよいでしょう。定期的にサービスの見直しを行い、より効果的な福利厚生プログラムへと改善していくことが健康経営の成功につながります。
まとめ
福利厚生サービスは従業員の健康増進を通じて、企業の生産性向上や人材確保・定着に大きく貢献します。本記事でご紹介したサービスの中から、自社の従業員にフィットするものは何かをよく検討してみてください。幅広い福利厚生サービスに備えたい場合は、無料付帯サービスが充実している団体長期障害所得補償保険(GLTD)が役立ちます。
企業がGLTD(団体長期傷害所得補償保険)を導入すれば、福利厚生の充実とあわせて多様な取り組みを実施できます。商品によってはストレスチェックの実施や24時間電話健康相談サービス、メンタルヘルスセミナーなどのサービスを活用できます。中小企業でできる取り組みを検討している場合には、検討してみてはいかがでしょうか。