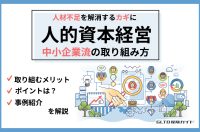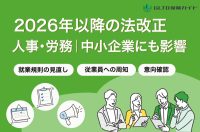近年、働き方に関する議論の中で「ワーク・ライフ・インテグレーション」という考え方が注目されています。
従来のワーク・ライフ・バランスが仕事と私生活を切り分けているのに対し、ワーク・ライフ・インテグレーションは、仕事と私生活を人生の一要素として一体にとらえ、相互に良い影響を与え合うことを目指すものです。
本記事ではワーク・ライフ・インテグレーションとは何か、注目される背景や企業が導入するメリットなど、労務担当者が押さえておきたい内容を解説します。自社における働き方を考える際のヒントとしてご活用ください。
ワーク・ライフ・インテグレーションとは?
コロナ禍を機にテレワークが普及し、オンオフが曖昧になる働き方が広がっています。こうした社会背景によって生まれた「ワーク・ライフ・インテグレーション」とは、ワーク(仕事)とライフ(私生活)を切り離さず、どちらも人生を構成する重要な一要素であるとして、一体的にとらえる考え方です。
仕事と私生活はどちらも人生に欠かせないものだからこそ、それぞれを高めあうことができれば、より良い相乗効果が生まれます。
つまり、働くことを通じて個々の人生を豊かにすることが、ワーク・ライフ・インテグレーションの目的です。
ワーク・ライフ・バランスとの違い
ワーク・ライフ・インテグレーションは、ワーク・ライフ・バランスの努力だけでは成しえない部分を補てんし、働く人の人生全体を支援しようとする考え方です。ワーク・ライフ・バランス:
仕事と生活を明確に分け、人生の貴重な時間やエネルギーをうまく配分してバランスを取る考え方
ワーク・ライフ・インテグレーション:
仕事と生活を一体にとらえ、それぞれを充実させることで相互に良い影響を生み出し、人生全体の満足度を高める考え方
これらの考え方は「どちらが正しい」という二項対立で見るものではありません。
あくまで、ワーク・ライフ・バランスの延長線上にある考え方がインテグレーションです。
企業としては、従業員の価値観やライフステージに応じて両方の考えを柔軟に取り入れることが求められます。
ワーク・ライフ・インテグレーションが注目される背景
ワーク・ライフ・インテグレーションが注目される背景には、テレワークの拡大や共働き世帯の増加といった社会変化が挙げられます。●テレワークの拡大
国土交通省の「テレワーク人口実態調査」(令和6年度)※1によると、雇用型テレワーカーの割合は全国で24.6%に達しました。在宅ワークやワーケーションなど、場所や時間にとらわれない働き方は今後もどんどん拡大すると予想されます。
●働き方改革の推進
政府が長年推進してきた働き方改革の浸透も、テレワークを含めた柔軟な働き方を後押ししています。フレックスタイム制や時短勤務制度の導入、副業の解禁により、働くことの概念がどんどん変わってきています。
●共働き世帯の増加
共働き世帯は年々増加しており、2024年時点でおよそ1,300万世帯※2に上ります。育児や介護と仕事の両立ニーズは今後もますます強くなり、柔軟な働き方が求められるでしょう。
社会全体の変化にあわせて、今後も働き方の柔軟化は進むでしょう。しかし、柔軟さは自由をもたらす一方で、オンオフが曖昧になるという側面ももたらします。
柔軟な働き方を健全に機能させるためには、仕事の延長線上にある人生の幸福度・充実度を考える視点が不可欠です。だからこそ、仕事を通じて人生そのものを支援するワーク・ライフ・インテグレーションの考え方が注目されているのではないでしょうか。
※1出所:国土交通省「テレワーク人口実態調査」(令和6年度)
※2出所:独立行政法人労働政策研究・研修機構「共働き世帯の状況」

ワーク・ライフ・インテグレーションを導入するメリット
ワーク・ライフ・インテグレーションの導入は、従業員と企業の双方にとって大きなメリットをもたらします。柔軟な働き方によって生活の質と人生の幸福度が向上すれば、従業員エンゲージメントが自然と向上し、心身の健康維持につながります。会社への帰属意識やモチベーションが高まり、人材の定着率アップにもつながるでしょう。また、心身の健康維持によって業務効率が改善すれば、生産性の向上も期待できます。
結果として組織全体のモチベーションや生産性が上がれば、企業競争力も強化できるのではないでしょうか。
ワーク・ライフ・インテグレーションを取り入れる働き方とは
株式会社マイナビの調査※によれば、「ワーク・ライフ・インテグレーションを実現できている人は働く時間や場所に柔軟性がある」傾向があります。一方で、実現できていない人の要因には、「通勤時間が長い」「サービス残業が多い」といった不満の声があることもわかりました。
これらの調査結果をもとに考えると、ワーク・ライフ・インテグレーションの実現には、時間と場所を柔軟にコントロールできる働き方が重要です。
【「時間」と「場所」の柔軟性を高める制度】
・ 時短勤務制度:育児や介護と両立しやすい
・ フレックスタイム制度:個人の生活リズムに合わせた働き方が可能
・ 時差出勤制度:通勤混雑の回避、私生活の用事との両立が容易
・ テレワーク制度:通勤時間を削減し、家族や趣味に時間を充てやすい
ただし、先述したとおり柔軟な働き方は仕事と私生活の境界線を曖昧にします。場所や時間を問わず働けることで、「常に仕事のことを考えてしまい、逆に疲労が蓄積する」という人もいるでしょう。
企業としてこれらの制度を提供する際は、時間や場所を柔軟にしつつ、働き過ぎないように制限を設けることが重要です。
テレワーク導入でオフィス代を削減し、その分を従業員の健康管理や福利厚生費用に充当する方法もよいでしょう。
出所:株式会社マイナビ「正社員のワークライフ・インテグレーション調査2025年(2024年実績)」
まとめ
ワーク・ライフ・インテグレーションは、従業員の人生を豊かにするだけでなく、企業にとっても人材確保や生産性向上につながる重要な考え方です。テレワークや時短勤務制度などで柔軟な働き方を取り入れていきましょう。 ただし、柔軟な働き方はオンオフの曖昧化による健康リスクをもたらします。企業は働き方の制度設計に加えて、従業員の健康管理や福利厚生の充実も意識することが大切です。GLTD保険(団体長期障害所得補償保険)は、病気やケガで長期間働けない人の収入をサポートする団体保険です。柔軟な働き方を健全に機能させるためにも、働く人の人生を守るGLTDの導入もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。