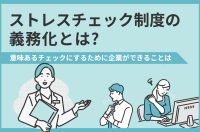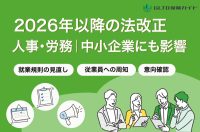「がん」は、日本人の約半数が一生に一度はかかるほど身近な病気です。働く世代でがんに罹患する人も多く、従業員を抱える企業にとっても無関係ではありません。
一方で、近年は医療の進歩により、治療を受けながら働き続ける従業員も増えています。
少子化が進む中、限られた人材を確保して事業を継続するためには、「がんと就労の両立支援」に取り組む企業作りが不可欠と言えるでしょう。
そこで本記事では、実際に中小企業で実践できる具体的な両立支援策を解説します。
従業員ががんに罹患する前からできる事前準備から、実際に罹患したときのフォロー、治療後の職場復帰まで、実務で必要な対応をまとめています。ぜひ参考にしてください。
がん患者の4人に1人は就労年齢で罹患している
がんは高齢者だけがかかる病気ではありません。統計※1によると、がん患者のおよそ4人に1 人が15~64歳の就労年齢でがんに罹患しています。
男女ともに年齢を重ねるほど罹患率が高くなり、特に女性は40歳代で乳がんの発症リスクが上がる傾向があります。
一方で、少子化で労働力が不足していることもあり、近年は女性や高齢者の就労が活発化しています。
今度も労働者の多様化が進むことを考えると、企業内にがん患者が現れる可能性はさらに高まるでしょう。
※1 参考:厚生労働省健康局がん・疾病対策課
「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」
がん治療のために休職や退職を選ぶ従業員も
早期発見と治療によって、がんは長く付き合える可能性のある病気になってきました。治療を受けながら働き続けるケースも増えており、「がん罹患=即退職」という時代ではありません。
ところが、実際のがん患者の調査報告書を見ると、がん治療のために休職や退職を選択している人が一定数いることがわかります。
【がん患者体験調査報告の内容】
・がんと診断時に仕事をしていた人:全体の44.1%
・そのうち、治療のために休職・休業した人:53.4%
・そのうち、治療のために退職・廃業した人:19.4%
※2 参考:国立がん研究センター 構成労働省委託事業「患者体験調査報告書 令和5年度調査」
なお、退職・廃業した人のうち約6割の人が初回治療の前に退職・廃業しています。これは治療と仕事の両立が見通せず、社内の相談体制が整っていなかったことも一因と考えられます。
企業においては、従業員ががんと診断される前から社内の相談体制を整えておく必要があるでしょう。
がんによる離職は企業にとって大きな損失
企業にとって、がんを理由に有能な人材を失うことは大きな損失です。また、病気になった従業員が退職を選べば、職場の雰囲気や従業員エンゲージメントにも悪影響を与えます。
誰か1人が退職することで「この職場では病気になったら辞めなければならない」という風土が生まれることは徹底して避けなければなりません。
がんに限らず、人生には結婚や出産、家族の介護といったライフイベントが発生しうる可能性があります。
ライフステージの変化に応じて柔軟に働き方を調整できる職場こそ、企業の持続的な成長を支える鍵となるのではないでしょうか。
【事前準備編】がんと仕事の両立支援のためにおくこと
企業のがん対策の第一歩は、「従業員ががんになったときに相談しやすい職場作り」から始まります。ここでは、従業員ががんと診断される前から始めておきたい、両立支援の準備方法について解説します。
1.情報収集しておく
まずは人事部や管理部門などが主体となり、がんに関する基礎知識や最新の治療動向、利用可能な公的制度について情報収集しましょう。収集した情報は体系的に整理し、社内の勉強会などを通じて適宜役職者中心に共有することをおすすめします。
がんについて正しい知識と情報を持つ上司がいれば、従業員にとって心強い相談相手になります。また、がん予防の啓発活動にもなるでしょう。
2.社内制度の整備
がんに罹患した従業員が活用できる制度を検討し、職場環境に応じて導入しましょう。社内で導入・活用できる制度には下記のようなものがあります。
・時間単位の年次有給休暇:本来1日単位の付与を、時間単位で付与できるようにする
・傷病休暇・病気休暇:年次有給休暇とは別に休暇を付与する
・短時間勤務制度:育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別に、病気療養中の負担軽減を目的に労働時間を短縮する制度
・時差出勤制度:始業や就業時間を変更し、身体に負担のかかる通勤時間帯を避ける制度
・テレワーク(在宅勤務):パソコン等を活用して自宅で勤務できるようにし、通勤による身体への負担を軽減する制度
業務内容や職場の状況によって活用できる制度は異なります。
いざというときに従業員が活用しやすく、自社の環境に適した制度は何かを精査しておきましょう。
3.相談窓口を設置して社内周知
人事部や管理部門、役職者などが相談窓口となり、「病気になっても相談できる職場」であることを周知させましょう。 がんになった従業員が黙って退職してしまう要因には、相談しづらい職場環境も作用していると考えられます。まずは「病気になったら誰に相談すべきか」「休業手続きなどの書類はどこに提出すればよいのか」を明文化し、社内に周知することが重要です。 社内周知の方法には、パンフレットの配布やポスターの啓示、社員説明会などの実施があります。役職者からも定期的に声がけを行い、相談しやすい職場環境を作っていきましょう。
【実務編】実際にがんと診断された社員に向き合う
実際に従業員ががんと診断されたら、企業としてどう対応すればよいのでしょうか。ここでは、実際に従業員ががんと診断されたときの実務について解説します。1.初期対応の基本
企業が最初に示す反応が、従業員との信頼関係や就労継続に大きな影響を与えます。初期対応の際は「本人の意向を何より尊重する」「会社として全面的に支援し、かつプライバシーに配慮する」ことを伝え、傾聴と支援の姿勢を明確に出すようにしてください。 がんは個別性の高い病気のため、人によって病状も進行速度も大きく異なります。
決して「もう働けないのでは」といった先入観で話を進めてはいけません。まずは話を聞き、本人の希望を引き出すことが大切です。
2.両立支援のための調整事項
従業員に就労継続の意思がある場合、どのような形で就労が可能かをすり合わせていきます。まずは通院・手術などのスケジュールや治療の影響をヒアリングし、業務の負荷をもとに業務内容を見直しましょう。
業務の調整は企業が一方的に行うのではなく、従業員と企業の双方で調整するようにしてください。
業務を調整する際は、先述した社内制度が活用できます。
たとえば、週3日の時短勤務とテレワークを併用すれば、通勤の負担を大きく抑えられます。実際に時短勤務やテレワークを組み合わせることで治療と仕事を両立しているケースもあるため、制度の導入は検討してみてください。
3.職場の理解と柔軟な運用
がんを抱える従業員のサポートは職場全体の課題です。本人の希望を尊重しつつ、チームでの業務分担やコミュニケーションの調整を行いましょう。特に気を付けたいのは過剰な配慮です。
病気を気にするあまり「まったく仕事を振らない」状態になると。従業員の孤立を深めてしまう可能性があります。
従業員本人の希望も考慮しながら、適度に業務負荷を調整するようにしてください。
4.治療後の復職支援
治療を終えた従業員が休職から復帰する際、フル稼働の即時復帰は現実的ではありません。治療後の身体はまだ本調子ではないことが多く、段階的な復職支援が必要です。
そのため、職場復帰の際は必ず面談を実施し、今後の課題と体調をよく確認してください。
復帰後一定期間は短時間勤務や週3日勤務などにして、段階的にフルタイムに戻していくのが理想です。
企業ができる支援策「GLTD保険」とは?
がんなどの病気で長期にわたり働けなくなると、収入減少と治療費負担という経済的ダメージが大きくなります。こんなときに役立つのが、長期の就業不能に備えるGLTD(団体長期障害所得補償保険)です。
GLTDは、従業員が病気やケガで長期休業した際の収入減少に備える団体保険です。
一部の商品にはがんを含む三大疾病の特約があり、付帯すれば治療のために短時間勤務をしている場合でも収入補償を受けやすくなります。
このほか、GLTDには福利厚生に関するさまざまな無料付帯サービスがあります。がん対策を強化して福利厚生を充実させたい企業は検討してみるとよいでしょう。
まとめ
がんと共生できる時代において、がんと仕事の両立支援は、企業にとって避けて通れない経営課題の一つです。本記事で紹介したポイントをもとに、まずは「がんになっても相談しやすい職場環境」を構築していきましょう。
がんと仕事の両立支援策として、GLTD(団体長期障害所得補償保険)に三大疾病特約を付帯する方法もあります。がんなどで長期療養時の収入減少をカバーできる団体保険で、比較的低コストで導入できるのが特徴です。
GLTDがあれば従業員は治療に専念でき、一方で企業は大切な従業員の離職を防ぐことができます。団体保険の導入は企業イメージや従業員満足度の向上にもつながるため、両立支援策を考えている企業は検討候補に入れてみてください。